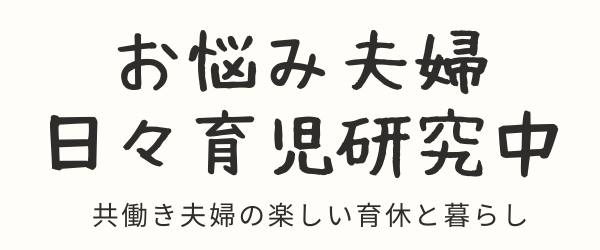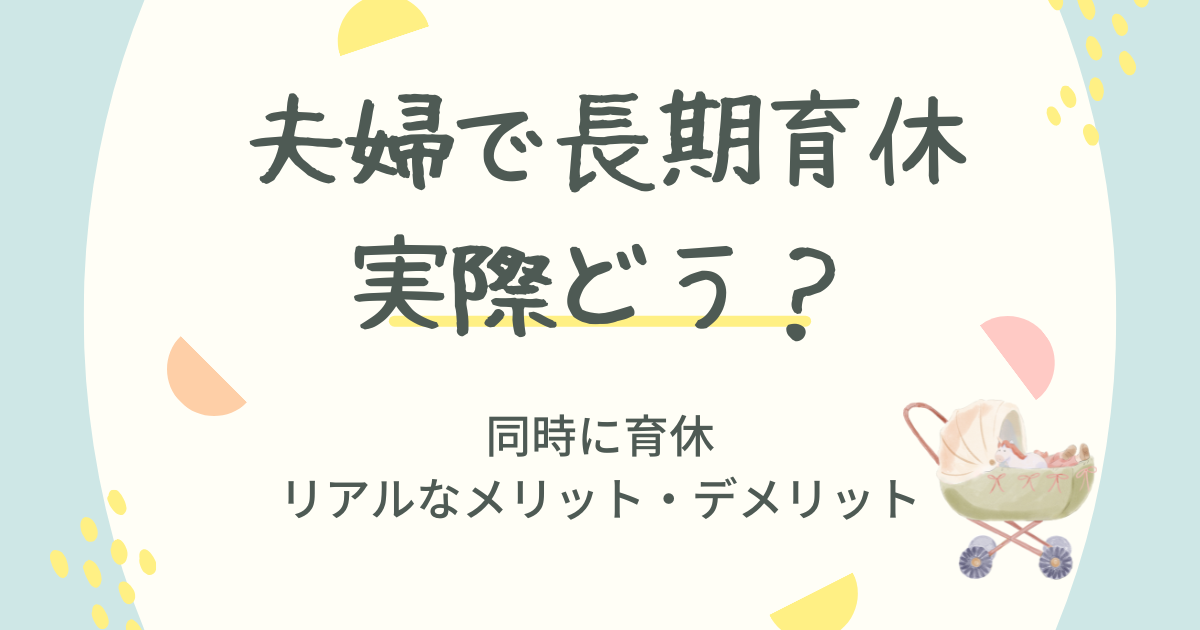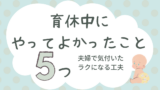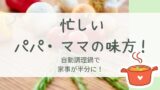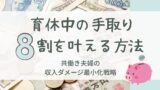夫婦で育休を取るかどうか、迷っていませんか?
「収入はどうなるの?」「一緒にいるとストレスにならない?」など、気になることも多いですよね。
私たちは現在、5歳と0歳の子どもを育てながら、夫婦で長期育休中です😊
両親は遠方(新幹線の距離)に住んでいるため、完全に夫婦2人で協力しながら育児をしています。
この記事では、実際に夫婦で育休を取って感じた“良かったこと”と“大変だったこと”を本音で紹介します。
これから育休を取ろうか迷っている方の参考になれば嬉しいです🌿
🌸育休中にやっておくと復帰後が楽になる準備については、
→夫婦育休中にやって良かったこと5選
で詳しくまとめています💡
良かったこと
子どもの成長を一緒に見守れた
いちばん良かったのは、夫婦そろって子どもの成長を間近で見られたこと。
「初めて立った!」「初めてしゃべった!」といった瞬間を、どちらか一方だけでなく2人で一緒に喜べるのは何よりの幸せでした🥰
子どもたちにとっても、ママもパパもそばにいる時間が長いことで、安心感が大きいように感じます。
心に余裕ができ、子育てがより楽しくなった
一人目の産後は、ママが体調を崩しがちで「育児が楽しい」と感じるまでに時間がかかりました。
でも二人目の出産後は、パパも同時に育休取得。
産後すぐから家事・育児を分担できたことで、ママは体をしっかり休めることができ、気持ちにも余裕が生まれました。
「子どもってかわいい!」と感じる時間がぐっと増えました✨
💡ちなみに、育休中に限らず、時短家電(食洗機、ロボット掃除機、自動調理鍋など)を使って家事を省エネ化するのはとってもオススメです!自動調理鍋については、
→【子育て家庭の必需品】自動調理鍋の魅力と使い方
で詳しく紹介しています!まだ導入していないかたはぜひ参考にしてください✨
上の子にしっかり向き合えた
二人目が生まれて急にお兄ちゃんになった上の子。
うれしさと戸惑いが入り混じる中、夫婦で育休中だったからこそ、上の子の気持ちに寄り添う時間を確保できました。

ママが下の子のお世話をしている間は、パパが上の子と全力で遊ぶ。
逆に、パパが下の子の寝かしつけをしている間に、ママが絵本を読んだり、ぎゅっと抱きしめたり。
「ママもパパも自分を見てくれている」という安心感が、徐々に上の子の落ち着きにつながったと感じています。
なんでも話し合える関係に
四六時中一緒に過ごしているからこそ、困ったことや不満を溜め込まずにすぐ話せます。
上の子が寝てから「夫婦時間」をとって、日々の悩みや明日の予定を共有。
たまに言い合いになることもありますが🤣、お互いの理解が深まったと感じます。
夫婦ともに”育児スキル”が上がった
夫婦で育休を取ったことで、授乳以外はどちらも一通りこなせるようになりました。
オムツ替え・寝かしつけ・離乳食づくりなど、どちらか一方が倒れても回る家庭に。

共働きで家事をシェアしてきた延長で、自然と「育児もシェア」できるようになりました。
平日に家族旅行や帰省ができた
育休中は仕事のスケジュールを気にせず動けるのが大きな魅力!
実家への帰省も、子連れでも無理のないスケジュールで行けました。
また、上の子のために旅行にも出かけましたが、平日割&空いている施設で快適に楽しめました🚅
大変だったこと
収入の減少
産休・育休中(1年目)はありがたいことに給付金をいただき、貯金を切り崩さずに生活できました。
ただ、パパが2年目の育休(無給)に入ると、やはり家計のやりくりは課題になると感じています💰
現在は支出を見直し、ふるさと納税や家計簿アプリを活用してやりくりを頑張る予定です💪🏻
育休中のお金についての想定と対策は
→【保存版】共働き夫婦の育休お金シミュレーション
で詳しくまとめています 💰
タイミングの違いによる切り替えの多さ
夫婦で育休を取ると、家族全体のリズムを何度も調整する必要があります。
産後すぐはパパとママが協力体制。
その後、ママが復帰し、パパのみの育休になると家事・育児の役割が一気に変化。
さらに、パパの復帰が近づくと、今度は「再び社会に戻る準備」が必要になります。
このように生活が段階的に変わるため、その都度の切り替えが意外と大変になりそうです。
分担のあいまいさ
夫婦で一緒にいる時間が長いと、「どちらがやるか」があいまいになりがちです。
ある日のお出かけ前、お互いに「オムツは相手が準備した」と思い込み、
出先で気づいたらオムツが1枚もなかったというハプニングも…!😱💦
慌ててドラッグストアに駆け込んで、反省会。
夫婦で育休を取ると、すべてを“なんとなく一緒にやっている”状態になりやすいです。
だからこそ、タスクを明確に言語化して共有することが大切だと実感しました。
まとめ|夫婦で育休を取って本当によかった
育休を夫婦で取るには勇気も調整も必要ですが、得られる経験は本当に大きいです。
子どもと一緒に過ごす日々は、お金では買えない時間。
大変なこともありますが、家族で過ごしたこの時間が、今後の人生の大きな財産になると感じています。
同じように育休を考えている方へ、少しでも参考になれば嬉しいです🐣
こちらも参考にどうぞ✨